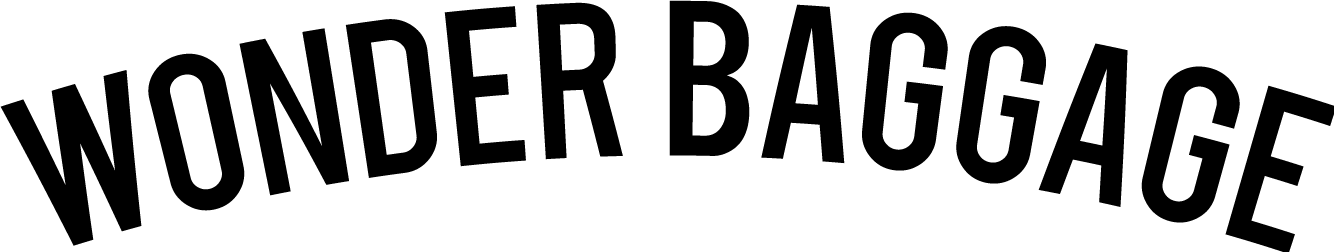洗えるレザーグローブの舞台裏|SETOUCHI LEATHERが語る透明なものづくりと、ホース/シープの選び方
ブランドの定番アイテムとして人気の「洗えるレザーグローブ」。
今回はこの洗える革と手袋を作った「SETOUCHI LEATHER(セトウチレザー)」の江浪弘芳氏(以下江浪)にインタビューを実施。革づくりや、プロダクトに対する想いを語っていただいた。
そこでまずは、セトウチレザーの業態を知ってもらうため、革を扱う業者について簡単に説明を行う。革は原皮と呼ばれる動物の皮を剥いだ状態のものから始まり、そこから何工程も重ねながら革となっていく工程をたどる、この工程を行うのがタンナーと呼ばれる業者。そして様々な革を販売する業者が革問屋と呼ばれている。そこから、革となった状態を革製品へと加工するのが製品製造業者だ。
- タンナー:動物の皮を「なめし」という工程で革へと加工する職人や会社。皮(スキン)を腐らないように処理し、長く使える革(レザー)へと仕立てる。
- 革問屋: 国内外のタンナーから革を調達し、個人や製造工場へ流通させる。
- 製品製造業者: 鞄・靴・手袋など最終製品に仕立てる職人や工場。
セトウチレザーの業態はタンナーとして分類されているが、それだけにとどまらない。通常、タンナーは革の製造のみが一般的だが、革を流通させる問屋業も備え、さらには製品づくりまで提案できるのが特徴。設立は2018年と歴は浅く、代表の二人も革業界においては非常に若く、様々な革新的な取り組みを行っている。

瀬戸内地域を拠点とするタンナー「セトウチレザー」
2018年に井上將裕、江浪弘芳により設立。井上が兵庫で皮革の製造・販売を、江浪が香川で革製品づくりと販売を担当。
本来は産業廃棄物として捨てられる皮を再生し、環境・社会・動物資源の循環に貢献する“サステナブルな革づくり”を目指す。
https://setouchileather.co.jp/
廃棄される皮を素晴らしい資源へ
セトウチレザーで扱う皮の多くの原皮(ゲンピ)は瀬戸内地域の食肉加工場から買い取った副産物とされており、本来なら廃棄されてしまうものとされている。彼らはその副産物から革をつくることを重要視する。
我々が目にしている革にも、その出自には様々な背景が存在する。例えば皮革が有名な一部の国や地域では、美しい革を作るために、動物の体に傷をつけないよう飼育される場合がある。つまりその動物は革となるために存在するということだ。
一方、食肉用として育てられた動物の皮は事情が異なる。人間が生きる為、肉を得ることが目的とされている。その副産物として生まれた皮を革として再利用するということになる。

「生きていた動物だからこそ、個性があるのは当たり前ということを知ってもらいたい」
そうした食肉用の皮はシワや、すり傷といった“生きた証”が残る。当然加工の過程で表面に顔料を塗布してキズを隠すことも可能だが、江浪はあえて「染色した後の革に着色剤や仕上げ剤などの薬品をあまり使用せず、革本来の表情を残したまま仕上げている。」と、素上げを推奨する。
それは一貫して、革を扱う業者としての立場表明であり、これからの社会と継続させるためのタンナーとしての矜持。そしてそれこそがセトウチレザーの原点となるのだと感じさせた。

産地表示の違和感─ものづくりの信念
「瀬戸内で作るなら、皮革も瀬戸内産であるべきだと思うんです」
セトウチレザーの、ものづくりの信念は前職(レザーグローブ製品工場)の経験が影響している。
前職である製品工場の現場では、イタリアで生まれた原皮を別の国で加工し、日本で“イタリアンレザー”として販売することがあった。そうした産地表示と実態のズレに、強い違和感を抱いたのだそう。
そこで江浪は「トレーサビリティ」を意識するようになった。
- トレーサビリティ:原皮がどこで生まれ、どこで鞣され、どこで製品になったのか──素材の流れをさかのぼって確認できる仕組み。 事業者や消費者は自分の手もとにある製品が「どこから来たのかわかる(=遡及できる)」
「瀬戸内地域で作った皮革を、瀬戸内で加工して製品化する方がストーリーも分かりやすいし、人の顔も見える。革を通して人に繋がる、そういう活動がしたいんです」
だからこそ江浪は縫製を香川県東かがわ市の手袋職人に縫製を託している。本当の「メイド・イン・セトウチ」と言えるものを作りたい。その一貫した透明性を意識しているからこそ、皮革から製品、販売まで携わった方の名前が全てわかることが重要だと話す。

「理想としては「製作者◯◯さん」と名前を出したいくらいです。映画のエンドロールは携わった制作スタッフや会社がわかりますよね?製品でも同じように、誰が関わったのか見えたらいいのにと思うんです。いろいろな問題で現実には難しいですけど(笑)」
こうした“顔が見えるものづくり”への思いが、セトウチレザーのプロダクトに反映されている。江浪の信念は透明性であること、そして使用する革の持続性、無駄のなさ。瀬戸内の地で生まれ、瀬戸内で育まれた革。そこに込められた信念が手袋となり、一双ごとにわずかな表情の違いをまとい、私たちのグローブへ受け継がれている。
手袋を手に取ったとき、その背景にある人の想いを感じてほしいために。
選べる二つの個性。ホース&シープ

WONDER BAGGAGE のウォッシャブルレザーグローブといえば、まずはホースレザー。馬革は牛革の約3倍といわれる強度を持ちながら、しなやかで艶やか。その丈夫さと扱いやすさは、多くのお客様から支持されています。手袋にしたときの安心感、使うほどに馴染む心地よさが魅力です。
一方、今回新たに加わるのはシープレザー(羊革)。初めて姫路で革を見せていただいた際、その弾力と“もっちり”した柔らかさには思わず「これはいいですね!」と声が漏れたほど。手にすっと馴染む感触は、シープならでは。
ここで改めて、それぞれの特徴を整理。

革の力強さを感じられるホースレザーと、柔らかく上品な表情のシープ。
二つの個性を選べるようになったことで、今年のWONDER BAGGAGEウォッシャブルレザーグローブは、より幅広いスタイルや好みに応えられる一双となりました。
WONDER BAGGAGEの「洗える」レザーグローブ。

「本当に洗っていいの?」「水に弱いんじゃないの?」と疑問に思う方は少なくありません。
この問いを江浪にぶつけてみると、意外な答えが返ってきた。
実はスポーツの世界では、20〜30年前から“洗える革”が当たり前に使われているのだそう。ゴルフや野球のグローブは汗やニオイを避けられず、洗えることが必須条件。
一方で、ビジネスやファッションの分野ではまだ知られておらず、新しい価値提案になっているとのこと。
ただし「色落ち」は永遠の課題だと江浪は言う。
革は水分や摩擦の影響を受けやすく、汗の成分や使用環境によっても色の変化が起こりやすい素材。
「デニムは色落ちが味わいとして歓迎されるのに、革の色落ちは欠点だと言われてしまう。不思議ですよね」
それでも、なめしの工程や厚みを工夫し、洗濯機でのテストまで重ねながら、洗える革を追求。
「合成皮革は買ったその日が100点。でもそこからは減点方式。一方で本革は、買った日が100点。その後の育て方次第で150点、200点にもなる」
つまり本革は“加点方式の素材”。その魅力に「洗える」という機能を掛け合わせたのが、WONDER BAGGAGEのウォッシャブルレザーグローブ。
いい革とは

最後に「いい革とは何か」を尋ねると、江浪は少し照れくさそうに答えた。
「私が大好きだと思える革です」
会社を立ち上げた頃、井上が作った馬革に初めて触れたときの感触。
江浪はその一枚に惚れ込み、1枚だけ自分のために買い取り自宅に保管している。
今もその革が、江浪のものづくりの基準であり続けているという。
「大好きだ」という純粋な感情から始まるものづくり。
その姿勢は、WONDER BAGGAGEのウォッシャブルレザーグローブの中にも確かに息づいている。その延長線上に生まれたグローブを、手に取って、日々使っていただければと思う。